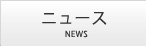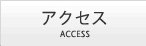JBICでは、バイオ関連基盤技術における幅広い分野を対象とした研究会を開催しています。
本研究会はJBIC会員企業限定の研究会であり、会員企業の要望や提案を取り入れて、バイオ関連分野の最新の研究内容、技術、動向等について企業やアカデミアより講師を招き、今後の取り組むべき方向性や産業応用の可能性について議論しています。
第52回テーマ「多様化する創薬モダリティの中での低分子医薬品:低分子医薬品の再考」 開催日 2026/1/15
| 発表タイトル |
講師 |
| グローバルにおける創薬トレンドと低分子薬の可能性 |
久保田 文先生(日経バイオテク編集長) |
第51回テーマ「適用が広がるAI創薬:臨床における生成AIの活用」 開催日 2025/11/18
| 発表タイトル |
講師 |
| 生成AIによるRWD活用とドラッグ・ロス解消に向けた取り組み |
勝田 江朗先生(富士通株式会社 Healthy Living事業部Digital Health PFグループ シニアディレクター) |
第50回テーマ「MPS(生体模倣システム)への期待と課題:FDAのロードマップが示すもの」 開催日 2025/09/24
| 発表タイトル |
講師 |
| 国内外の事例にみるMPSの開発動向と行政利用に向けた取り組みと課題 |
石田 誠一先生(崇城大学 生物生命学部 応用生命科学科 教授) |
第49回テーマ「スマートラボの現状と将来:AI創薬とラボオートメーションがもたらすもの」 開催日 2025/07/03
| 発表タイトル |
講師 |
| 人・AI・ロボットが共創する未来の創薬へ:アステラス製薬の事例 |
田端 健司先生(アステラス製薬株式会社イノベーションラボ グローバルヘッド Advanced Modeling & Assay) |
| 生命科学実験におけるAI最適化技術と自動化連携の応用と展望 |
小澤 陽介先生(エピストラ株式会社 CEO) |
第48回テーマ:心臓再生遺伝子治療の最前線:基礎から臨床へ 開催日 2025/01/16
| 発表タイトル |
講師 |
| 心不全に対する新しい心臓再生遺伝子治療の開発 |
家田 真樹先生(慶應義塾大学医学部 循環器内科 教授) |
第47回テーマ:miRNA創薬の最前線 開催日 2024/12/26
| 発表タイトル |
講師 |
| 創運動器疾患治療を目指した革新的RNA創薬と力学的制御機構の解明 |
淺原 弘嗣(東京科学大学 システム発生・再生医学分野 教授) |
運動器疾患の治療法開発において、RNA制御と力学的シグナルの理解は重要な基盤となっている。我々は、マイクロRNA(miRNA)と力学的シグナル伝達の両面から、革新的な治療戦略の開発を進めている。miRNAは22塩基程度のノンコーディングRNAで、特異的なターゲットmRNAの翻訳を抑制する制御分子として注目し、関節リウマチにおけるmiR-146や変形性関節症におけるmiR-140の重要性をいち早く唱え、miRNAと慢性炎症の医療応用研究をリードしてきた。これらに基づき、内因性miRNAの分子基盤を応用した新規人工核酸を開発し、疾患を憎悪させる複数の遺伝子を同時に抑制する革新的なモダリティの開発に成功し、臨床応用に向けた研究に取り組んでいる。一方、腱組織の研究では、マスター転写因子Mkxを同定、さらに、メカノセンサーPIEZO1の機能的多型E756delがジャマイカのトップスプリンターに高頻度で存在することを発見した。この知見に基づき、Piezo1-Mkx経路の機能解析を進め、腱特異的なPiezo1機能獲得マウスにおいて運動能力の顕著な向上を実証した。この作用機序を基盤として、運動機能を賦活し、腱・靱帯損傷の治癒を促進する創薬開発を行っている。
▲閉じる
|
第46回テーマ:AI創薬の現状と将来:国内ベンチャーの先進的取り組み 開催日 2024/09/04
| 発表タイトル |
講師 |
| 大規模分子基盤モデルによる次世代AI創薬 |
島田 幸輝(SyntheticGestalt社 CEO) |
大規模事前学習モデルが注目を集めており、テキストや画像分野では GPT-4 などの成功例があるが、分子や化合物の分野では十分な発展がなく、従来のAI 創薬には、学習データ外での低精度や専門家の知見を超えられないという課題を解決するため、事前学習を活用した大規模分子モデル「SG4D1B」を開発した。他の著名なモデルと比較して、学習データ量と特徴量の次元数で優位性を示し、分子情報を取り扱った事前学習モデルとしては現在世界最大のモデルとなっている。実際の評価としても、学習データ内および実利用データにおいて高い精度を実現した。特に、事前学習により獲得した分子の一般的な特徴理解が、新規分子や少量データでのタスクにおいても高い性能をもたらした。新たな創薬の可能性について概説する。
▲閉じる
|
| 大規模言語モデルを活用した中・高分子医薬品開発 |
玉木 聡志(Molcure社 CEO) |
わが社は、独自のAIを用いた創薬プラットフォーム(PF)を開発し、製薬企業およびバイオテック企業との共同研究をビジネスモデルとするスタートアップ企業である。このPFは、「Target-to-hit」フェーズから「Lead Optimization」フェーズまでをカバーし、医薬品候補分子を効率的に提示可能である。本PFは、アメリカの製薬企業との共同開発プロジェクトにおいて、単独開発と比較して 10 倍以上の医薬品候補を発見し、100 倍以上の結合力を持つ候補分子を特定する成果を上げた。創薬分野における生成 AI の応用、また AI 駆動科学の将来展望について紹介する。
▲閉じる
|
第45回テーマ:AI創薬の現状と将来 開催日 2024/05/23
| 発表タイトル |
講師 |
| AI創薬導入における国内外ギャップと将来展望 |
山田 泰永(エヌビディア合同会社 ヘルスケア開発者支援) |
2010年代から始まったディープラーニングAIの発展は、ChatGTPをはじめとする大規模言語モデルと生成AIが大きく進展し、創薬・ライフサイエンス領域でも本格的な活用が普及し、初期の実績も上がりつつある。本講演ではまずAI・計算創薬全体を概説し、具体的なアプリケーションや活用事例を取り上げる。特に欧米のAI主導型の創薬スタートアップ企業や一部のメガファーマはすでに多様なAIを日常業務に組み込んでおり、独自の大規模基盤モデルを学習・構築し、「ラボ・イン・ループ」型でAI予測・生成とハイスループットのシミュレーションやウェット実験結果を組み合わせて、継続的に学習し高効率な研究開発を展開している。また海外では、政府も関与してライフサイエンス分野にほぼ特化したAI基盤の事例も出てきた。これらの事例も取り上げ、日本における本格的なAI創薬実現に向けた課題を考える。
▲閉じる
|
第44回テーマ:次世代CAR-T細胞の開発 開催日 2024/03/08
| 発表タイトル |
講師 |
| 次世代CAR-T細胞の開発 |
籠谷 勇紀(慶應義塾大学医学部 先端医科学研究所 がん免疫研究部門 教授) |
がん抗原特異的に認識する抗腫瘍T細胞を体外で準備して患者に輸注する養子免疫療法の中でも、キメラ抗原受容体(chimeric antigen receptor: CAR)導入T細胞療法はB細胞性腫瘍、多発性骨髄腫などの実臨床への導入が進んでいる。しかし長期観察では再発例が多く、また、固形がんへの客観的な有効性は十分でない。T細胞の寿命、及びがん細胞と微小環境などが惹起する抗腫瘍T細胞の機能低下(疲弊)が、持続的な治療効果を阻む原因である。また、サイトカイン放出症候群のような重篤な副作用制御の観点も重要である。一方、本療法は体外でT細胞の培養・増殖工程を含むことから、細胞自体のシグナル伝達経路について遺伝子レベルでの加工が容易である。近年、T細胞の生存能や疲弊に関わるメカニズム解析が進み、修飾すべき遺伝子群が解明されているが、改変によるT細胞の腫瘍化リスクも考慮しなければならない。また、製造コストの観点から、他家由来NK細胞を活用したCAR-NK細胞の開発が着目されている。さらに、抗体を用いて生体内のT細胞に抗原特異性を付与する二重特異性抗体は、持続的な効果が高まれば細胞療法よりも利便性に優れている。上記のトピックスに関する現状について、我々の研究室で得られたデータを交えてお話しする。
▲閉じる
|
第43回テーマ:治療用がんワクチン 開催日 2023/11/21
| 発表タイトル |
講師 |
| 治療用がんワクチンの再興 |
垣見 和宏(近畿大学医学部 免疫学教室 主任教授) |
2000年初頭、日本でもペプチドがんワクチン開発が精力的に進められたが、臨床試験において有効性を示せなかった。免疫チェックポイント阻害剤の登場で、Hodiらにより2010 年NEJMで初めて抵抗性の転移性メラノーマ患者の全生存率を改善した画期的な治療法であると報告された。このように、チェックポイント阻害剤の登場から10年たって、周回遅れでがんワクチンが再注目されている。しかし、がんワクチン研究は根強く継続されていた。COVID-19パンデミックへの対応を可能にしたのは、治療用mRNAがんワクチン設計を改善するための研究データの蓄積によるものである。がんに対する免疫応答の主役である腫瘍特異的CD8+T細胞は、個々のがん細胞が持つ遺伝子変異産物から生じたネオアンチゲンを認識している。Biontech社は、このネオアンチゲンに対する治療用がんワクチン開発のトップランナーであり、また、Moderna社もMerckの抗PD-1抗体とネオアンチゲンを標的としたがんワクチンを併用した臨床試験の結果を発表し注目されている。
▲閉じる
|
第42回テーマ:次世代抗体医薬 開催日 2023/09/26
| 発表タイトル |
講師 |
| 中外製薬における抗体創薬の過去、現在、未来 Past, present, and future of antibody drug discovery in Chugai |
倉持 太一(中外製薬株式会社 研究本部 バイオ医薬研究部長) |
抗体医薬品は、がんや免疫炎症性疾患領域を中心に100品目を超える医薬品が承認されており、抗体エンジニアリング技術が市場拡大を支えてきた。初期課題であったマウス由来モノクローナル抗体の免疫原性がキメラ化抗体やヒト化抗体により解決され、抗体半減期の延長による利便性の改善、親和性の向上、抗体依存性細胞傷害、補体依存性細胞傷害増強による薬効向上など、抗体医薬品創生技術が大きく発展している。
わが社では、これらに加え、新しい抗体エンジニアリング技術開発に取り組んできた。具体的には、抗体が繰り返し抗原に結合できるリサイクリング抗体®技術、免疫複合体を積極的に細胞内に取り込むことで血中の抗原濃度を低下させるスイーピング抗体®技術、がん病変部位において抗原特異的に機能を発揮するスイッチ抗体™技術、左右の抗原結合部位で異なる抗原に結合できるバイスペシフィック抗体製造技術、1つのFabが2つの標的に結合することができる次世代T細胞バイスペシフィック抗体技術などが挙げられる。わが社の抗体エンジニアリング技術について紹介するとともに、機械学習を利用した抗体医薬品プロセスの革新について述べる。
▲閉じる
|
第41回テーマ:乳がん診療 開催日 2023/07/12
| 発表タイトル |
講師 |
| 乳がんにおける最近の診療トピックスについて |
戸井 雅和(都立駒込病院 院長、京都大学名誉教授) |
2000年に乳がんサブタイプの概念が提唱され、2010年ころから異なる5つ以上のサブタイプの治療法開発が行われるようになった。乳がんにおいてホルモン受容体陰性でHER2陰性のがんが免疫療法の主対象になっている。また、antibody-drug-conjugate (ADC)もHER2-lowというサブタイプをまたぐ対象で実施され、BRCA1/2に病的変異を持つ乳がん症例にはPARP阻害治療法も導入されてきた。加えて、予後の予測と治療効果の予測を精密に行う手法も進化しており、リスクの程度に応じた治療戦略も開発された。同時に診断法の開発も進展しており、病勢の把握、モニタリング、早期発見の観点で血液を用いたliquid biopsy診断法の開発が進んでいる。このような、最近の乳がん診療のトピックを紹介する。
▲閉じる
|
第40回テーマ:核酸医薬 開催日 2022/11/16
| 発表タイトル |
講師 |
| 核酸医薬の創薬展開 ~ENAアンチセンスとMED-siRNA~ |
小泉 誠(第一三共株式会社 モダリティ研究所 主席) |
核酸医薬は、低分子化合物や抗体医薬では標的とすることができない分子に対して治療薬を設計することができるモダリティとして注目されている。2018~2022年にかけて、10品目の核酸医薬品が承認されている。特に遺伝性ATTRアミロイドーシス治療薬であるpatisiranはLNP技術と組み合わせたsiRNAであり、急性肝性ポルフィリン症治療薬であるgivosiranはGalNAcを結合したsiRNAで、ともに肝臓への送達を高めている。有用な核酸医薬品創製のため、阪大の小比賀先生は2‘-酸素原子と4’-炭素原子をメチレンで架橋したヌクレオシドMEDを見出している。新たに上記原子をエチレンで架橋したENAを創出し、エキソンスキッピング能を有するENAについて紹介する。合わせて、2’-O-methyl RNAとDNAを交互に配したMED-siRNAについてもその特性と機能について概説する。
▲閉じる
|
第39回テーマ:タンパク質分解誘導・基礎から創薬応用 開催日 2022/09/28
| 発表タイトル |
講師 |
| 選択的な標的タンパク質分解技術と創薬 |
内藤 幹彦(東京大学大学院 薬学系研究科 特任教授) |
近年、細胞内タンパク質を分解する技術が開発され、この技術を基盤とする創薬研究が活発に行われている。多発性骨髄腫などの治療に使用されるレナリドミドは一部の転写因子を分解する。このほか、PROTAC、SNIPERに代表されるキメラ化合物は標的リガンドとE3ユビキチンリガーゼ結合のリガンドとをリンカーでつないだ化合物である。標的リガンドを置換することで標的タンパク質分解を合理的にデザインできる注目の創薬プラットフォーム技術である。我々はcIAP1の自己ユビキチン化と分解を誘導するメチルべスタチンを基に新規SNIPER化合物を開発してきたので紹介する。また、タンパク質分解医薬品と従来モダリティとの比較研究などについても概説する。
▲閉じる
|
| 標的タンパク質分解誘導剤の効果を促進する細胞内因子の発見 |
大竹 史明(星薬科大学 先端生命科学研究所 特任准教授) |
標的タンパク質分解誘導技術は、疾患原因タンパク質をユビキチンリガーゼと近接させることで強制的にユビキチン化と分解を誘導する双頭性の化合物はPROTACと呼ばれる新規モダリティである。標的タンパク質にどのようなユビキチン鎖が形成され、どのように分解されるのかなど、PROTACの分子作用メカニズムは不明な点がある。PROTAC作用を促進するユビキチンリガーゼTRIP12を発見したので、この機能を解析することにより標的分子分解の効率を高める技術への展開が期待された。標的タンパク質分解の理解に重要なユビキチンコードについて概説し、我々の最近の知見を紹介する。
▲閉じる
|
第38回テーマ:ファージ療法を用いたマイクロバイオーム制御 開催日 2022/04/19
| 発表タイトル |
講師 |
| 腸内ウイルス叢のメタゲノム解析と治療応用 〜Viral Dark Matterへの挑戦〜 |
植松 智(大阪公立大学大学院医学研究科・医学部ゲノム免疫学 教授
東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター メタゲノム医学分野 特任教授) |
腸内細菌叢の構成異常は宿主の病態に大きな影響を与える。疾患の発症や病態に直接的にかかわる腸内強制病原菌(pathobiont)も同定され、これを制御することが疾患の予防や治療に役立つと考えられる。ヒト腸管常在微生物叢は細菌、ウイルス、真菌などから構成されている。腸内ウイルスの大部分はバクテリオファージであり、腸内細菌とウイルスの関係を絶妙に構築して共生している。多剤耐性最近問題などからファージ療法が再評価されつつあるが、腸内共生細菌を標的としたファージ療法はエビデンスが乏しいため有効活用できていない。我々は腸内ファージのゲノム解析法を確立し、pathobiontを制御するファージ同定とその溶菌酵素の活用、また、粘膜ワクチンを用いた制御法も併せて紹介する。
▲閉じる
|
第37回テーマ:ファージ療法 開催日 2021/12/01
| 発表タイトル |
講師 |
| ファージ療法の100年 〜歴史的背景から人工ファージの創出まで〜 |
安藤 弘樹(岐阜大学大学院医学研究科ファージバイオロジクス研究講座 特任准教授) |
第36回テーマ:新たなRNAアプタマー創製法の創薬への応用 開催日 2021/10/01
| 発表タイトル |
講師 |
| 膜受容体GPCRの活性制御を目的とした新たなRNAアプタマー創製法の開発 |
高橋 理貴(東京大学医科学研究所 RNA医科学社会連携研究部門 特任准教授) |
緊急開催:ゲノム進化からみた新型コロナワクチンと変異株 開催日 2021/08/20
| 発表タイトル |
講師 |
| ゲノム進化からみた新型コロナワクチンと変異株 |
五條堀 孝(アブドラ国王科学技術大学 特別栄誉教授) |
第35回テーマ:細胞内相分離研究・創薬への応用 開催日 2021/06/10
| 発表タイトル |
講師 |
| 非コードRNAによる細胞内相分離の誘導と機能制御 |
廣瀬 哲郎(大阪大学大学院生命機能研究科 RNA生体機能研究室 教授) |
第34回テーマ:プロテインノックダウン・新たな創薬ターゲット 開催日 2021/02/09
| 発表タイトル |
講師 |
| 標的タンパク質を特異的に分解する低分子薬の開発技術 |
大岡 伸通(国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部 室長) |
第33回テーマ:『バイオバンク横断検索システムと東北メディカル・メガバンク計画の進捗』 開催日 2020/12/18
| 発表タイトル |
講師 |
| ゲノム医療実現推進のためのバイオバンク・ネットワーク構築 |
荻島 創一(東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 教授) |
| 東北メディカル・メガバンク計画の進捗と産学連携 |
山本 雅之(東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 機構長) |
第32回テーマ:『エクソソーム研究』 開催日 2020/10/28
| 発表タイトル |
講師 |
| エクソソームのプロテオミクスを用いたがん診断および脳転移機構 |
星野 歩子(東京工業大学生命理工学コース 准教授) |
第31回テーマ:『肝疾患(NAFLD/NASH)と肝再生医療』 開催日 2019/11/25
| 発表タイトル |
講師 |
| NAFLD/NASHの臨床の現状 |
鎌田 佳宏 (大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 機能診断科学講座 准教授) |
| NASH病態解析と診断法・治療法開発を目的とした糖鎖研究 |
三善 英知 (大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 機能診断科学講座 教授) |
| ダイレクトリプログラミングによる機能性肝細胞の作出と肝再生医療 |
鈴木 淳史 (九州大学生体防御医学研究所 細胞機能制御学部門 器官発生再生学分野 教授) |
| 肝臓の脱細胞化骨格を用いた臓器再生の現状と展望 |
八木 洋 (慶應義塾大学医学部外科学教室 一般・消化器外科 専任講師) |
第30回テーマ:『遺伝子治療の最新状況』 開催日 2019/09/30
| 発表タイトル |
講師 |
| 遺伝子治療の開発と規制の現状と課題 |
内田 恵理子 (国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部第1室 室長) |
| 神経筋疾患に対する遺伝子細胞治療の課題と展望 |
岡田 尚巳 (東京大学医科学研究所 遺伝子・細胞治療センター 教授) |
| センダイウイルスベクターを用いた遺伝子治療製剤の開発 |
菊岡 正芳 (株式会社アイロムグループ 取締役 事業開発本部長) |
第29回テーマ:『ゲノム医療の最新状況』 開催日 2019/03/13
| 発表タイトル |
講師 |
| 未病社会に必要なプレシジョン・メディシン |
佐藤 孝明 (筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター センター長) |
| がんゲノム医療の現状と課題 |
高阪 真路 (国立がん研究センター研究所 細胞情報学分野 主任研究員) |
| がんゲノム医療における情報解析の現状 |
西村 邦裕 (株式会社テンクー 代表取締役社長) |
第28回テーマ:『検査・診断のための医療機器開発の最新状況』 開催日 2018/12/03
| 発表タイトル |
講師 |
| 経済産業省における医療機器産業政策について |
門川 員浩 (経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室 室長補佐) |
| 尿中腫瘍マーカーによるがん検査の可能性について |
坂入 実 (株式会社日立製作所 研究開発グループ 基礎研究センタ チーフサイエンティスト) |
| 深層学習を用いた胃病理診断支援技術の開発 |
荒井 敏 (オリンパス株式会社 画像技術部 部長) |
| 医療領域における数値シミュレーション、VR技術の展開 |
渡邉 正宏 (富士通株式会社 第二ヘルスケアソリューション事業本部 シニアマネージャー) |
第27回テーマ:『がん免疫療法の基礎と臨床の最新状況』 開催日 2018/09/11
| 発表タイトル |
講師 |
| がん微小環境研究から見たがん免疫療法 |
西川 博嘉 (名古屋大学大学院 医学系研究科 微生物・免疫学講座 分子細胞免疫学 教授
国立がん研究センター 研究所 腫瘍免疫分野/先端医療開発センター 免疫TR分野 分野長) |
| 免疫療法の臨床開発の現状と展望-消化器癌を中心に |
設楽 紘平 (国立がん研究センター 東病院 消化管内科 医長) |
| 免疫ゲノムプロファイルの多様性 |
油谷 浩幸 (東京大学先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス分野 教授) |
第26回テーマ:『AIによる病理画像診断の最新状況』 開催日 2018/07/03
| 発表タイトル |
講師 |
AIの医療応用への取り組み
~現状と展望~ |
山本 陽一朗 (理化学研究所 革新知能統合研究センター 病理情報学ユニット ユニットリーダー) |
| 人工知能によるゲノム病理情報の利活用 |
石川 俊平 (東京医科歯科大学難治疾患研究所 ゲノム病理学分野 教授) |
| 病理画像AI開発後の実際の運用-遠隔病理診断の経験を踏まえて- |
吉澤 明彦 (京都大学大学院 医学研究科附属 総合解剖センター 准教授) |
第25回テーマ:『Liquid Biopsyへの取り組み(第4弾)』 開催日 2018/02/27
| 発表タイトル |
講師 |
| 細胞外小胞顆粒エクソソームが織りなす光と影:新たな細胞間コミュニケーション因子による人体の恒常性維持と疾患への関わり |
小坂 展慶 (国立がん研究センター研究所 分子細胞治療研究分野 東京医科大学細胞外小胞顆粒創薬研究講座 特任研究員) |
| 小さな粒子エクソソームが切り開く大きな可能性~臨床・産業応用への可能性と問題点~ |
吉岡 祐亮 (国立がん研究センター研究所 分子細胞治療研究分野 研究員) |
| 細胞外小胞の不均一性の形成における膜ドメインの役割 |
原田 陽一郎 (鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 システム血栓制御学講座 特任准教授) |
| エクソソームを利用したアルツハイマー病予防・治療のための取り組み |
湯山 耕平 (北海道大学大学院 先端生命科学研究院 生体機能化学研究室 特任准教授) |
第24回テーマ:『Liquid Biopsyへの取り組み(第3弾)』 開催日 2017/11/29
| 発表タイトル |
講師 |
| 体液診断(Liquid Biopsy)関連分離・計測技術開発動向 |
高嶋 秀昭 (一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム 戦略企画本部) |
| がん転移再発の早期診断におけるctDNAの臨床的有用性について |
三森 功士 (九州大学病院別府病院 外科 教授) |
| マイクロ流体デバイスを用いたCTC解析プラットホームの構築 |
金 秀炫 (東京大学生産技術研究所 藤井研究室 助教) |
第23回テーマ:『エクソソーム研究開発』 開催日 2016/09/15
| 発表タイトル |
講師 |
| エクソソームを利用したがん早期診断法の開発 |
植田 幸嗣 (公益財団法人がん研究会 ゲノムセンター がんオーダーメイド医療開発プロジェクト プロジェクトリーダー) |
| がん転移先を規定するエクソソームとそのインテグリン発現パターン |
星野 歩子 (コーネル大学医学部 David Lyden研究室) |
第22回テーマ:『新規核酸医薬技術と臨床応用』 開催日 2015/12/11
| 発表タイトル |
講師 |
| 核酸医薬ルネサンス |
矢野 純一 (レナセラピューティクス株式会社 代表取締役社長) |
| 新規核酸医薬、ヘテロ核酸の創生 |
横田 隆徳 (東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経病態学分野 教授) |
| がん幹細胞を標的とした新規核酸医薬の現状 |
落谷 孝広 (国立がん研究センター 研究所 分子細胞治療研究分野 主任分野長) |
| デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬NS-065/NCNP-01の早期探索的臨床試験 |
齊藤 崇 (国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部 研究員) |
第21回テーマ:『ゲノム編集技術と創薬研究への応用』 開催日 2015/09/29
| 発表タイトル |
講師 |
| CRISPRの発見とその機能、ゲノム編集への応用の現状 |
石野 良純 (九州大学大学院農学研究院 生命機能科学部門 蛋白質化学工学分野 教授) |
| 疾患特異的ヒトiPS細胞とゲノム編集技術による新たな難病研究 - ダウン症候群をひとつの例として - |
北畠 康司 (大阪大学医学系研究科 小児科学講座 助教) |
| ミニ組織培養技術の応用:がんと幹細胞ニッチ |
佐藤 俊朗 (慶應義塾大学医学部 消化器内科 准教授) |
第20回テーマ:『Liquid Biopsyへの取り組み(第2弾)』 開催日 2015/07/23
| 発表タイトル |
講師 |
| DNAバーコード技術を使った高精度DNAシーケンシング |
久木田 洋児 (大阪府立成人病センター研究所 疾患分子遺伝学部門 主任研究員 ) |
| Liquid Biopsy実用化へ向けて |
的場 亮 (株式会社 DNAチップ研究所 代表取締役社長) |
| ナノバイオデバイスによるLiquid Biopsy |
馬場 嘉信 (名古屋大学大学院工学研究科 化学・生物工学専攻 教授・分野長) |
第19回テーマ:『Liquid Biopsyへの取り組み』 開催日 2015/04/08
| 発表タイトル |
講師 |
| 米国におけるLiquid Biopsyの取組み状況について |
高嶋 秀昭 (バイオ産業情報化コンソーシアム) |
| 血漿遊離DNAを用いたEGFR-TKI耐性化モニタリング |
荒金 尚子 (佐賀大学 医学部 血液・呼吸器・腫瘍内科 准教授) |
| Circulating tumor DNA解析技術の現状 |
加藤 菊也 (大阪府立成人病センター研究所 疾患分子遺伝学部門 部門長) |
第18回テーマ:『次世代創薬開発のための基盤技術~細胞内シグナル伝達と次世代抗体医薬(マイクロ抗体)~』 開催日 2014/08/08
| 発表タイトル |
講師 |
| 細胞内シグナル伝達機構の解明から創薬へ |
金保 安則 (筑波大学医学医療系(生命医科学域)生理化学研究室 教授) |
| 次世代抗体医薬“マイクロ抗体”:分子進化工学による分子標的ペプチドの創出 |
藤井 郁雄 (大阪府立大学 理学系研究科 教授)
|
第17回テーマ:『アカデミア創薬 / ドラッグ・リポジショニング』 開催日 2014/06/06
| 発表タイトル |
講師 |
| 医療・創薬におけるビッグデータの利用 |
田中 博 (東京医科歯科大学 難治疾患研究所 ゲノム応用医学部門 生命情報学分野 教授) |
| 新規ビッグデータ解析手法による精神神経系疾患診断系の検討 |
石井 一夫 (東京農工大学 農学府農学部 農学系ゲノム科学人材育成プログラム 特任教授) |
第15回テーマ:『ドラッグ・リポジショニングに向けてのアカデミアの取り組み(第2回)』 開催日 2014/01/24
| 発表タイトル |
講師 |
| ドラッグ・リポジショニングと創薬スクリーニング |
堀内 正 (慶應義塾大学 医学部 医化学教室 特任講師) |
| GSK3β阻害作用を持つ医薬品のリポジショニングによる進行膵癌の新規治療法開発 |
島崎 猛夫 (金沢医科大学 医学部 消化器内科学 講師) |
| ドラッグ・リポジショニングによる悪性脳腫瘍に対する新規化学療法 |
中田 光俊 (金沢大学 医薬保健研究領域 脳神経外科 講師) |
| 精神疾患へのドラッグ・リポジショニングの可能性 |
功刀 浩 (国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第三部 部長) |
第14回テーマ:1細胞質量分析とイメージング融合創薬の可能性 開催日 2013/11/22
| 発表タイトル |
講師 |
| 可視化1細胞質量分析と創薬 |
升島 努 (独立行政法人 理化学研究所 生命システム研究センター 一細胞質量分析研究チーム チームリーダー) |
| マルチカラーイメージング法を用いた細胞内セカンドメッセンジャー挙動の解析 |
岡 浩太郎 (慶應義塾大学 理工学部 生命情報学科 教授) |
第13回テーマ:ドラッグ・リポジショニングに向けてのアカデミックへの期待と取り組み 開催日 2013/10/02
| 発表タイトル |
講師 |
| In vitro virus(IVV)法のゲノム創薬への展開 |
柳川 弘志 (慶應義塾大学 訪問教授・NPO横浜ライフサイエンス研究機構 会長・IDACセラノスティクス(株) 科学顧問) |
| 千葉大医学部 アカデミック臨床研究機関(ARO)の取り組み |
佐藤 喬俊 (千葉大学 医学部付属病院 臨床試験部 プロジェクトリーダー室 特任教授・室長) |
第12回テーマ:分子イメージング技術の最新動向とその応用 開催日 2012/09/26
| 発表タイトル |
講師 |
| 細胞内外の空間を考慮したシミュレータ:RICSの開発 |
横田 秀夫 (理化学研究所・和光研究所基幹研究所・先端技術基盤部門生物情報基盤構築チームヘッド) |
| SACLAとSPring-8を利用した非結晶粒子のコヒーレントX線回折イメージング |
中迫 雅由 (慶應義塾大学理工学部物理学科 教授) |
第11回テーマ:プロテオーム解析の最新動向 開催日 2012/05/09
| 発表タイトル |
講師 |
| 蛋白質相互作用解析と創薬 |
津本 浩平 (東京大学医科学研究所 疾患プロテオミクスラボラトリー 教授) |
| 質量分析装置の最先端創薬への応用 |
佐藤 孝明 (株式会社島津製作所・ライフサイエンス研究所 所長) |
第10回テーマ:個別化医療を実現するバイオマーカー 開催日 2012/2/24
| 発表タイトル |
講師 |
| リバーストランスレーショナルリサーチが可能にする機能性癌マーカーの探索 |
仙波 憲太郎 (早稲田大学 先進理工学部生命医科学科 教授) |
| スパコンが焙り出すがんのシステムとしての薬剤応答性、個性 |
宮野 悟 (東京大学 医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 教授) |
第9回テーマ:世界最速コンピュータ「京」とIT創薬 開催日 2011/11/22
| 発表タイトル |
講師 |
| 京速コンピュータ「京」の開発状況について |
横川 三津夫 (理化学研究所 次世代スーパーコンピュータ開発実施本部開発グループ グループディレクター) |
| スーパーコンピュータを用いた創薬に向けて |
藤谷 秀章 (東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授) |
| 分子シミュレーションによる第一原理的なドッキングやフォールディング」-57残基蛋白質や天然変性蛋白質の自由エネルギー地形 |
肥後 順一 (大阪大学 蛋白質研究所 客員教授) |
第8回テーマ:iPS細胞実用化への取り組み~新規因子Glis1と網膜再生医療~ 開催日 2011/09/15
| 発表タイトル |
講師 |
| 転写因子Glis1による安全かつ効率的なiPS細胞の作製 |
五島 直樹 (産業技術総合研究所 バイオメディシナル情報研究センター 主任研究員) |
| iPS細胞を用いた網膜再生医療 |
高橋 政代 (理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター網膜再生医療研究チーム チームリーダー) |
| 京都大学iPS細胞研究所CiRAでの研究開発状況 |
青井 貴之 (京都大学 iPS細胞研究所 規制科学部門 教授) |
| iPSアカデミアジャパン(株)でのライセンス活動の紹介 |
白橋 光臣 (iPSアカデミアジャパン株式会社 ライセンス部 部長) |
第7回テーマ:JBIC会員企業における技術開発の取り組み 開催日 2010/10/22
| 発表タイトル |
講師 |
| プレシジョン・システム・サイエンス社におけるシステム開発サイドから見た研究から臨床への進展 |
田島 秀二 (プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 代表取締役社長) |
| 島津製作所の診断・医療機器開発の現状 |
濱崎 勇二 (株式会社島津製作所 分析計測事業部産学官・プロジェクト推進室 副室長) |
| 大規模並列計算環境を活用する富士通のIT創薬 |
松本 俊二 (富士通株式会社 バイオIT事業開発本部IT創薬推進室 室長) |
第6回テーマ:ケモバイオPJの成果活用について 開催日 2010/09/14
| 発表タイトル |
講師 |
| タンパク質相互作用ネットワーク解析による疾患メカニズムの解明 |
夏目 徹 (産業技術総合研究所 バイオメディシナル情報研究センター) |
| 天然物ライブラリーを用いた化合物スクリーニング |
新家 一男 (産業技術総合研究所 バイオメディシナル情報研究センター) |
| タンパク質相互作用を標的としたインシリコ解析 |
広川 貴次 (産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター) |
第5回テーマ:創薬や医療への情報技術の活用 開催日 2010/06/24
| 発表タイトル |
講師 |
| 次世代オミックス医療のインパクト |
田中 博 (東京医科歯科大学大学院 生命情報科学教育部 教授) |
| インシリコ創薬による新薬創出の効率化に向けた取組み |
古谷 利夫 (株式会社ファルマデザイン 代表取締役社長) |
第4回テーマ:創薬・診断のための機器開発とその応用 開催日 2010/05/20
| 発表タイトル |
講師 |
| 網羅的な自己抗体解析による疾患診断法ならびに治療法の開発 |
五島 直樹 (産業技術総合研究所 バイオメディシナル情報研究センター 主任研究員) |
| 世界標準を志向したmiRNAと核酸医薬のマススペクトロメトリー |
鈴木 勉 (東京大学大学院 工学系研究科 化学生命工学専攻 教授) |
第3回テーマ:微生物の更なる活用を目指して 開催日 2010/04/21
| 発表タイトル |
講師 |
| 放線菌の二次代謝産物生合成研究とその応用 |
大西 康夫 (東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授) |
| ゲノムからメタゲノムへ |
黒川 顕 (東京工業大学大学院 生命理工学研究科 教授) |
第2回テーマ:次世代シーケンサーとシステム生物学 開催日 2010/03/19
| 発表タイトル |
講師 |
| 次世代シークエンサーを用いたトランスクリプトーム解析 |
鈴木 穣 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科 准教授) |
| システム生物学的アプローチによる分子相互作用解明のための基盤技術-ネットワーク解析による創薬ターゲット絞込み- |
堀本 勝久 (産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター 研究チーム長) |
第1回テーマ:核酸医薬(技術)の課題 開催日 2010/02/26
| 発表タイトル |
講師 |
| 製薬企業から見た核酸医薬の課題と今後:-国内発の核酸医薬創製に向けて- |
矢野 純一 (日本新薬株式会社 取締役) |
| RNA研究からRNAi創薬へ-siRNA医薬による肝癌の分子標的治療 |
古市 泰宏 (株式会社ジーンケア研究所 代表取締役会長) |
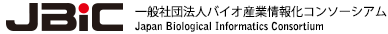






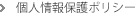
 ENGLISH
ENGLISH